
卓球愛を封印した5歳児
ブログ

ブログ
こちらは『卓球レディース』編集長の西村が、NOルールで綴る馬鹿馬鹿しい卓球日記です。今回は私が初めて卓球に触れた時のこと。卓球を始めるきっかけって人それぞれですよね。
全日本ホカバの試合。未来のスター選手のプレーはもちろんのこと、その親御さんの華やかな顔ぶれにも目を奪われますよね。「えっ、もしかしてプロリーグの、元オリンピアンの、名門〇〇クラブの、元日本代表の……」。日本の未来を背負う子供たちの親は、日本の現在を背負うor過去に背負ったスター選手という可能性が高い。愛ちゃんや美誠ちゃんのお母さんも実業団出身ですものね。「卓球はトンビが鷹を産むことはないのかな……」そう思わざるを得ません。
私の母親は詩吟の師範でした。エロ詩吟ではなく、正統派です。母のおなかに宿った瞬間から詩吟を聴かされて育ち、物心がつく頃には毎日4時間稽古させられていました。まさに英才教育。その点では卓球少女と呼ばれるお子さんたちと同じような育ち方かもしれませんね。泣きながらも一生懸命プレーする愛ちゃんや美誠ちゃんをテレビで見ると、玄関に立たされ泣きながら発声練習をした幼い頃の自分と重なります。当時の私の日常は詩吟一色だったのですが、ある日、違う色のクレヨンを見つけてしまいました。それも押入れの中で。
ある雨の日、外遊びができず退屈をもてあましていた私は押入れの中を探検することにしました。知らない物がたくさん眠っている押入れは5歳児にとって宝島のよう。冒険家気分で奥の方まであさっていたところ、お宝を発見しました。見るからに上等な洋菓子の缶が押入れの隅っこに置かれていたのです。鮮やかな色彩で描かれた花柄のフタ。ふちが少し錆びていて時を経た香りがする。年代物のお宝をゲットした興奮で鼻息が荒くなりました。私は剝ぎ取るようにフタを開けると、中は金銀財宝ではなく〇〇でした。濁色のゴムが貼られた木の板、赤茶けた古布と冊子、そして網と小さな白い玉。私は家で事務仕事をしているお母さんのところへ持っていき、「これ何?」と尋ねました。すると母は「どこで見つけたの?」と驚いて、すぐにフタをしめて押入れの中にしまいました。私は押入れをグチャグチャにした罪でこっぴどく叱られました。
次の日、懲りない私はお菓子の缶を押入れから出してきてもう一度母に尋ねました。何をするものかと。母は「これはピンポン。羽根つきみたいなもの」と教えてくれました。私は羽根つきが大好き。「やりたい、やりたい」と母にせがみました。母は仕方がないなと事務仕事の手をやめ、詩吟のカセットテープを取りに行きました。「やばい。また稽古させられる!!!!!」仕事を中断させた罰として、詩吟の練習をさせられると思った私は、缶を見つけたことを心底後悔しました。
ところが、母はカセットテープをデッキに入れずにテーブルの中央に並べました。そして板を使って白い玉を打ち合う遊びを教えてくれました。
私は教えられた通り、板の柄を鉛筆持ちして振ってみました。けれどボールがなかなかあたらない。やっとボールが当たるようになると、ピンポンという代物は羽根つきとは比べ物にならないくらいおもしろかった。なぜならお母さんが本気で遊んでくれたから。どんなところにボールが飛んでいってもお母さんは意地でも追いつき、拾う。拾う。拾う。どんなに玉を打ちあげても、あさっての方向に飛ばしても、私の小さな懐に白い玉が返ってきます。詩吟の舞台では直立不動の母の姿からは想像がつかない華麗な玉さばき。ピンポンの躍動感あふれる舞に私はキャッキャと大興奮。
その次の日も押入れから缶を出してきて、母にピンポンをせがみました。今度は自分でテーブルの中央にカセットテープを並べ準備万端。母はまた仕事を中断して遊びにつき合ってくれました。「お母さんはなんでこんなにピンポンが上手いの?」と尋ねると母は「ピンポンの選手だった」と教えてくれました。その瞬間、私の世界に光が差しました。詩吟一色のグレーのキャンバス、そこに深紅のクレヨンがさっと線を描いたのです。「お母さんは詩吟だけの人ではなかったんだ」。私の幼い心の扉は外に向かって大きく開かれました。家族との会話は詩吟オンリー。だけど、よかったんだと。詩吟以外のことを話してもいい、興味を持っていい、やってもいいんだと。母が元選手だというのなら、私はピンポンをやってみたい。きっと喜んでやらせてくれる、教えてくれるに違いない。
翌日、私は覚悟を決めて押入れから缶を出しました。そして母にピンポンをせがむと、遊びではなく真剣に板をふりました。母は昨日と同じように楽しそうに相手をしてくれます。優しそうな笑顔。その表情に安堵して勇気を振り絞り伝えました。「お母さん、私はお母さんに詩吟じゃなくピンポンを習いたい。私もお母さんみたいな選手になりたい」。
すると母の表情は明から暗へ。私を真正面から見据えて「ラケットふってみ」と言いました。私は2、3回素振りをすると、母は「あかんなー、素質がない」と失笑。そしてピンポンの道具をすべて缶にしまい。私の目を見てこう言いました。「ピンポンのことは忘れて、詩吟をがんばりなさい」。母は缶を押入れにしまいに行きました。
(独白)ははーん、お母ちゃんは知らない。わたしのしつこさを!!!!!
そう、私は弁当箱に染みついたカレー臭のような5歳児。
次の次の次の日も私は押入れに缶をとりに行きました。しかし見当たりません。私は冒険王よろしくの探求心で押入れの中をグチャグチャにし、缶を探し当てました。缶は押入れの奥の奥の奥に隠されていました。
そして、お母さんのもとへ缶を持っていき、「お母ちゃん。私は真剣にピンポン習いたいねん。詩吟じゃなくてピンポン教えて」と懇願しました。
すると、母の顔色がさっと変わりました。そして「ピンポンはやるのもアカン、興味を持つのも絶対にアカン。どうしても気になるというなら、お母さんは今すぐこの缶の中身を焼き捨てる!!!!!!」ヒステリックな物言いでたたみかけられた私は恐怖心で涙すら出ませんでした。いつもニコニコの母の表情が激しく崩れる瞬間を見てしまった。押入れの缶も母の鬼の形相も見てはいけないものだったのです。そして、母を怒らせたり悲しませたりせぬよう、二度とピンポンはしないと幼心に誓いました。
それから10年後、私は自我の芽生えとともに高校の卓球部に入るのですが……あれ、お母ちゃん、間違ってトンビを産んでまっせ。

インタビュー
2025.06.10

グッズ
2021.04.28
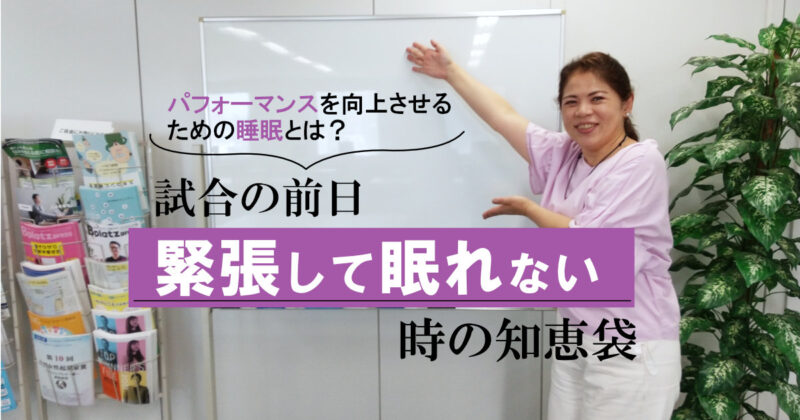
メンタル
2021.06.12

テクニック, ブログ
2024.06.07

インタビュー
2025.03.28

グッズ
2021.04.28
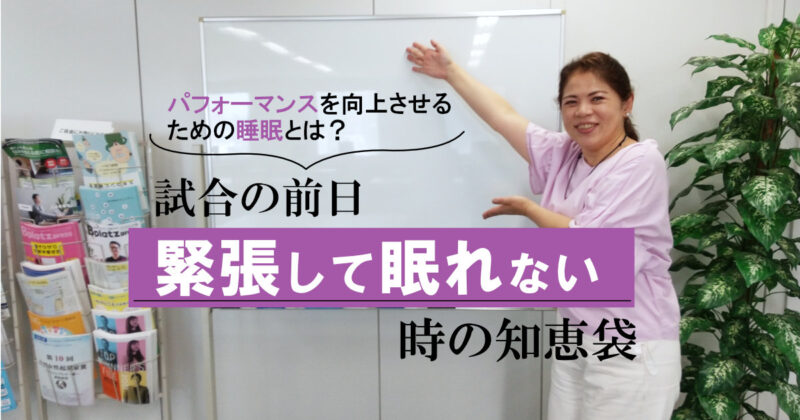
メンタル
2021.06.12

グッズ
2022.08.24

インタビュー
2023.10.31

グッズ
2021.10.20