
ラケットの僕とご主人様
ブログ

ブログ
近畿大学の学生さんが卓球レディースのために書いてくれた卓球小説。卓球未経験の大学生が卓球をテーマにストーリーを考えると、人間ではなく用具が主人公になるんですね。ふむふむ。なななんと……これはおもしろい!
夏のある日のこと。
セミの鳴き声が響き渡る。まるでお互いを認め合い、1つの輪が出来たかのように。
この日はアマチュアの卓球大会の日。ご主人様が出場するため、私ことラケットの”あかまる”がお供をする。今大会は親睦会という意味が込められて、1 ゲームだけの試合となる。
「あっつー、バックの中ってなんでこんな熱が籠るんだよ、、、」
ご主人様のバックに入っていた僕は、あまりの暑さに呻き(うめき)を漏らした。それから20分後、ドスンと床に荷物が置かれた衝撃。すぐにチャックから木漏れ日が差すかのように体育館の明かりが荷物の中を照らしてきた。僕はご主人様が試合を楽しみにしていた気持ちが伝わるかのように優しく、強く、握り絞められた。反対の手にはタオルがご主人様の汗を拭っていた。
ご主人様はストレッチを15分程し、アップを始めた。少しばかり緊張しているせいか、思うように上手くコントロールが出来ていない様子。すると
「今日は不調かもしれないのぉ、、、」と、ご主人様がボソッと嘆いた。
試合がまもなく始まるため、両者のラケット交換が握手と共に行われた。そのとき僕は驚愕した。なんと、相手のラケットの色が黄色だったのだ。ラケット同士がすれ違う瞬間、『弱そっ』と、笑い交じりの声に、僕を嘲る響きが混ざっていた。
「さっさとこの試合は終わらせるか」
と相手のご主人様が嫌味をこちら側に飛ばしてきやがった。まあ、よくもまぁ黄色ラケットと性格が似ているものだ。そんなこんなで試合が審判の合図と共に、台へ叩きつけられたボールの音が鳴り始めた。
まずは僕たちのサーブ。2回とも鋭いサーブを打ち、すぐに2ポイントを取り終えた。良かった。調子が戻ってきた。相手の攻撃だが至って普通だった。あんなにも悪い性格をしていたのにも関わらず、本当に普通だった。
しかも僕たちの方が強いのでは?と、無意識のうちに気の緩みへと繋がっていた。だが、そんな僕たちは相手の手の平で転がされていたということを知る由もなかった。僕たちが10点目になりマッチポイント。相手はまだ7点で余裕があった。
「この試合はもらったのぉ」と、ご主人様が勝利を確信している。僕もそう思っていた。
ご主人様のサーブが返され、あと1点までの長いラリーが続く。ここで試合が動く。
「あー、すいませんねー」
と相手が言った瞬間、ネットインで得点が取られた。そんな時もあるよな、と僕とご主人様は思っていた。しかしその後、同じやり方で2点連続取られてデュースとなった。
「さすがにこれは狙ってやっとるのぉ」とご主人様が見破った。
僕はその言葉を聞いてやっと気づく。それと同時にスポーツマンらしくないため、腹が立ち始めていた。相手がコントロール出来ないように全力でスマッシュを決め、僕たちはマッチポイントへ。
「ここで決める」
僕とご主人様の思いが重なり合い、手汗と握り強さからご主人様の緊張感が伝わってくる。左から上げられたボールは高く飛び上がり、最大火力で台へ叩きつけ、3回目のバウンドした時には体育館の床だった。あまりの速さに相手が反応できていなかったのだ。
「負けちった」
「負けるんかよ」
相手のご主人様と黄色ラケットが落ち込んでいるのが、後ろ姿から読み取れた。
「スカッとしたわー!」と、僕が一言。
試合終了の挨拶として両者が整列。握手が交わされ、うちのご主人様が「お互い本気で打ち込んで楽しむことが出来たわい。ありがとうの」と優しい言葉を相手に伝えた。
すると「あんな ラッキーが続いてしまってすまん」と相手のご主人様が謝罪した。
「お前たち、ほんとは強かったんだな」黄色ラケットが、自分の立ち位置が無くなりながらも僕らへ伝えてくれた。
ご主人様たちは、僕たちを重ね合わせるようにして仲良く休憩スペースへと足を運んだ。
そこでは互いの漬物交換が始まり、親睦会が始まった。この大会では試合後に漬物交換をし、お互いのプレイや雑談を行う特別な文化がある。
試合前はあれほどバチバチな関係だったが、全力で戦い合った者同士だからこそ生まれる絆が生まれていたのだ。
セミの鳴き声が静まり返った頃。
僕たちラケットは仲良くなり、体育館中に選手同士の笑い声が響き渡る。
まるでお互いを認め合い、1つの輪が出来たかのように。

グッズ
2021.04.28

テクニック, ブログ
2024.06.07

インタビュー
2023.10.31

テクニック
2025.11.05

テクニック
2026.01.02

グッズ
2021.04.28
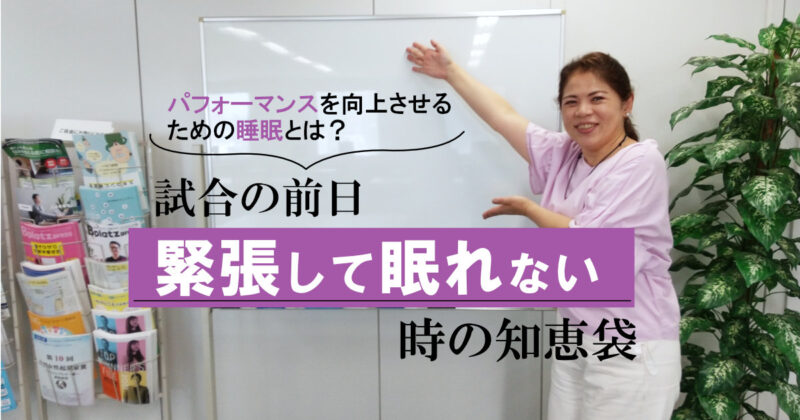
メンタル
2021.06.12

グッズ
2022.08.24

インタビュー
2023.10.31

グッズ
2023.09.05